病院を出たあとの沈黙の車内
診察室を出たあと、2人とも言葉を発さなかった。
病院の自動ドアが閉まる「プシュー」という音だけが、やけに耳に残る。
車に乗り込むと、ハンドルを握る主人の手が小刻みに震えていた。
信号待ちで赤に変わるたびに、眉間に深いシワを寄せ、何かを飲み込むように唇を結んでいた。
私は助手席で、何を言えばいいのかわからず、ただ前だけを見ていた。
「大丈夫だよ」なんて言葉は、この瞬間、あまりにも軽すぎて。
それよりも、彼の中で何かが崩れ落ちていく音を、確かに感じた。
窓の外では、いつもと変わらない街が流れていく。 平日の昼間にこうやって出かけることがないので、街をジョギングする人たちの姿さえ見たくもないし怒りさえ覚えた。
信号の青と赤が、無情に交互に点滅していた。
あのときほど「世界はこんなにも普通で、私たちだけが異世界に来てしまった」と感じた日はない。 世の中のすべてが敵に見えた。
息ができないほど苦しく、狭い車内が酸欠になりそうな空気。
医療従事者として病気と戦う人をたくさん見てきた。
当事者しかわからない、家族しかわからない、見えない心の内側が少しだけ「わかった気」がした。
午後3時、朝から何も食べずに病院に行ったのでお腹が空いて意識失いそうだったが隣の主人が何も発しない以上、お腹空いたなんて言えない。
お腹が空くことが幸せだから。
この重い空気が続くある時、主人の父親から電話がかかってきた。


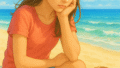





コメント