肺に影がある――告げられた瞬間
胸のレントゲンとCTを見ながら、診察室で並んで説明を受けていた。
「肺に影があります」――そう言われた瞬間、時間が止まったように感じた。
そして次に続いた言葉は、受け入れがたい現実だった。
「それがガンです」
診察室の空気が一気に重くなり、鼓動の音だけが自分の耳の奥で大きく響いた。
目の前の説明よりも、横に座る主人の表情の方が気になって仕方がなかった。
主人の表情に宿る恐怖
常に向上心を持ち、ミスや間違いを嫌い、病気など自分には無縁だと信じていた主人。
その主人の目が血走り、攻撃的で、恐怖に揺れていた――その姿が何よりも怖かった。
診察室で言葉を飲み込む私
呼吸器の主治医は50代。国立がん研究センターに長く従事し、今も研究を続ける頼れる存在だった。
また、セカンドオピニオンも推奨する病院で「他の病院でも診てもらってよい」と声をかけてくれた。
けれど、その会話は主人には届いていないようだった。
診察室では私は絶対に口を開けなかった。
本来の私なら主治医と対話できるのに、主人は他人に口を挟まれることを嫌う。
そのため、歯痒さを抱えつつ、ただ黙って隣に座り続けた。
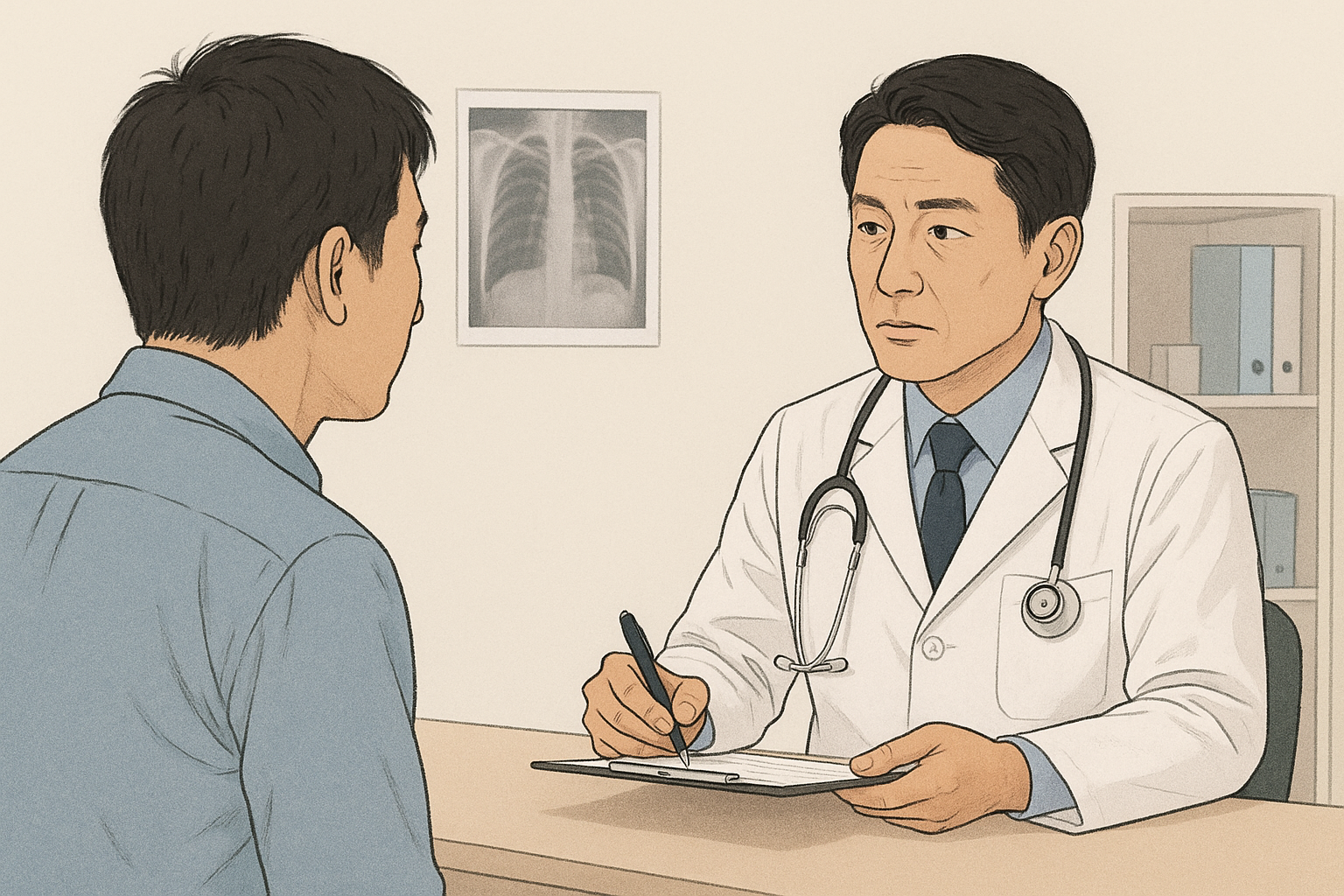
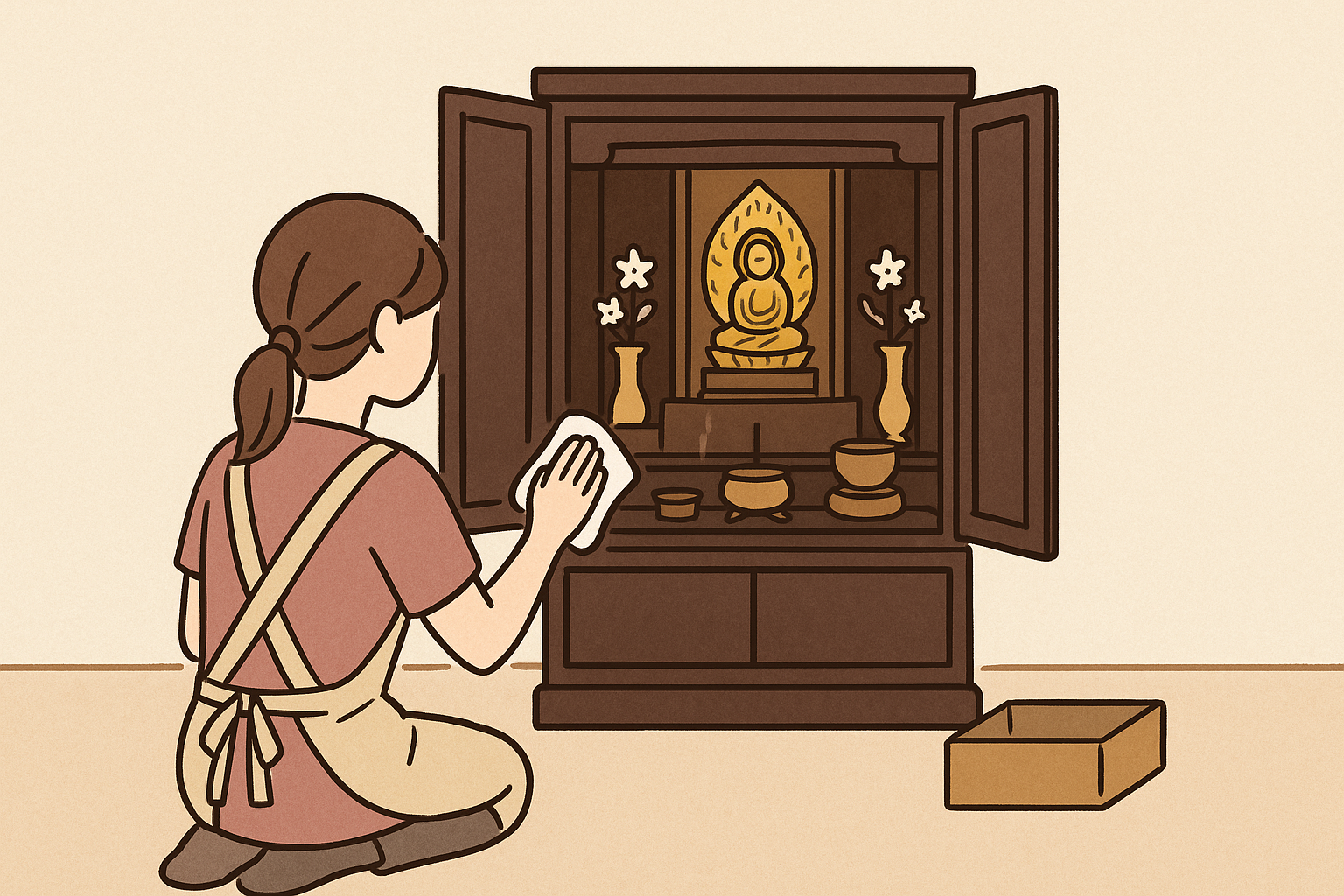






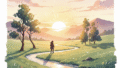
コメント